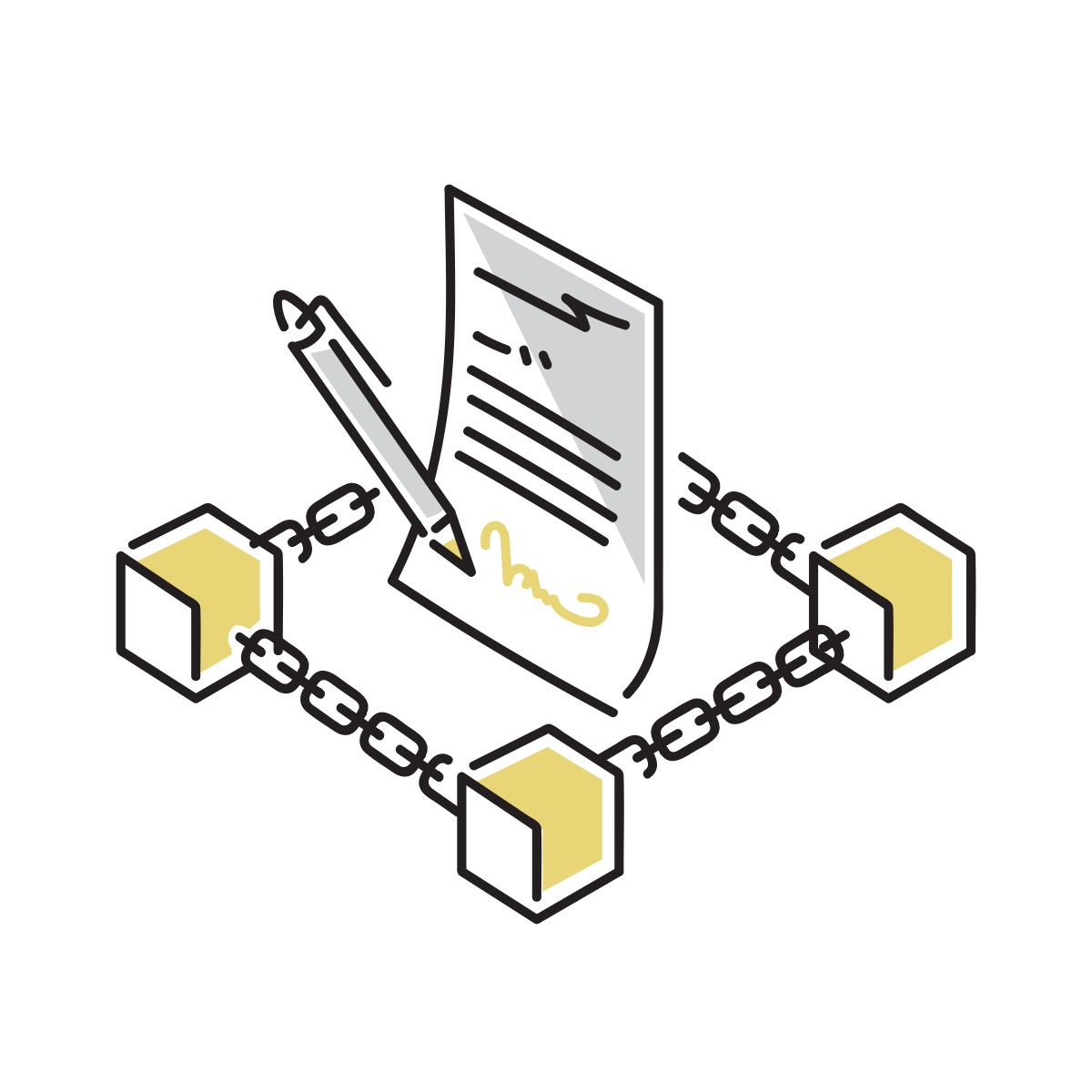こんにちは!宅建合格を目指して勉強中のアナです。
今回は「契約不適合による売主の担保責任」について、宅建試験でよく出題されるポイントをまとめてみました。
自分の理解を深めるためにも、実際の学びを言葉にしていきます。
いい復習にもなるので、書くことをみなさんにも是非おすすめしたいです!
契約不適合の場合の売主の担保責任
売主の担保責任とは、売買契約で引き渡された物に「契約と異なる内容(=契約不適合)」があった場合に、売主が買主に対して責任を負うことです。たとえば、中古住宅の売買で「雨漏りはありません」と説明されていたのに、実際は雨漏りしていた…というようなケースです。
このような場合、買主は売主に対していくつかの請求ができます。これが担保責任と呼ばれるものです。
追完請求
契約不適合があった場合に、まず買主が取れる手段が「追完請求」です。これは、契約通りの状態にするよう売主に求めること。たとえば、欠陥のある部分の修理や、足りないものの補充を求めます。
注意したいのは、追完請求をするには「不適合を知ったときから1年以内」に売主に通知しなければならないということ。この“通知”が遅れると、請求そのものができなくなってしまうので要注意です!
代金減額請求
次に「代金減額請求」。これは「修理してもらえない」「契約通りの状態には戻せない」といった場合に、買主が売主に対して代金の一部を返してもらうことができる制度です。
たとえば「壁の一部にシミがあってどうしても消えない」といった状況では、その部分に相当する金額を減額してもらえるという考え方ですね。追完ができないときの代替措置ともいえます。
原則、催促が必要になりますが、追完が不能の場合など催促しても無意味な場合などは催告せずに、直ちに代金減額請求ができます。
ただ、買主に落ち度があったら代金減額請求はもちろんできません。
損害賠償請求と契約解除
さらに、契約不適合によって損害を受けた場合には「損害賠償請求」ができます。
たとえば、修理に自腹で数十万円かかった…というときなどが該当します。
また、不適合の程度が大きくて契約の目的が達せられない場合は「契約解除」も可能です。
たとえば、シロアリ被害で住むこと自体が難しいなど、住居としての機能を果たせないような場合ですね。
担保責任の期間の制限
担保責任には「期限」があります。これは“買主が不適合を知ったときから1年以内に通知”というルール。これを過ぎると、追完請求・減額請求・損害賠償・解除など、すべての手段が使えなくなる可能性があります。
ただし、通知さえしておけば、その後に正式な請求をする猶予は少しありますので、まずは早めに売主へ「不具合があります」と伝えることが大切です。
例外として、売主が引渡しのときに不適合を知っていたり、重大な過失によって知らなかったとき、つまり売主が悪意があったり善意重過失であるときは買主は知った時から1年以内に通知しなかった場合でも追完請求・代金減額請求・契約解除ができます。
担保責任を負わない旨の特約
最後に、「売主が担保責任を負わない」という特約を契約で結ぶことも可能です。
ただしこれは万能ではなく、特に売主が業者(事業者)で買主が一般消費者である場合、こうした特約は無効になることがあります。
知りながら告げなかった事実についても売主は責任を免れることはできません。
消費者保護の観点から、業者が一方的に責任を免れるような条項は認められにくいということですね。
契約書の内容をしっかり読み、自分の立場がどうなるか確認することが重要です。
おわりに
「契約不適合と売主の担保責任」について、宅建の学習内容をベースにまとめてみました。
条文だけ読むと難しく感じるテーマですが、具体的な事例をイメージしながら整理すると、理解が深まります。
テキストを流し読みしているだけだと眠くなりそうな内容でしたが、手を動かしてまとめてみると頭に入ってきたような気がします!
同じく宅建を目指す方の参考になれば嬉しいです。
次回は「連帯債務・保証債務」についても掘り下げてみたいと思います!