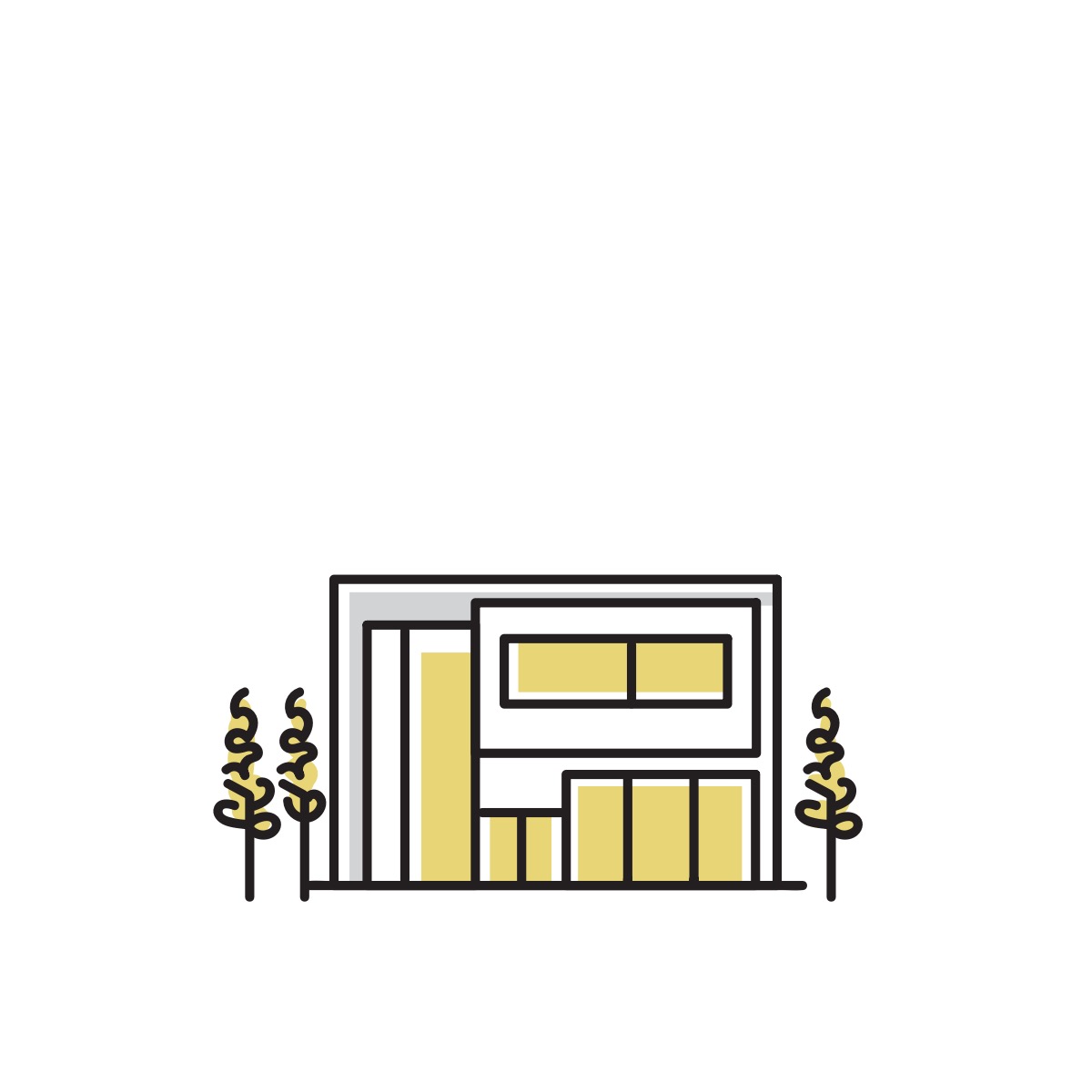こんにちは。宅建合格を目指しているアナです。
今回は「賃貸借」についてまとめてみました。
賃貸借契約って、日常生活でもなじみ深いですよね。アパートやマンションを借りるときに結ぶ契約がこれです。
でも、実際に法律的にどうなっているのかは、学んでみると意外と知らないことが多い!ということで、宅建試験でもよく出る6つのポイントに絞って整理していきます。
目次
賃貸人の義務は何か
賃貸人(貸主)の義務は、大きくわけて2つあります。
1つ目は、「使用・収益させる義務」。これは、借り主(賃借人)が契約通りに物件を使えるようにすること。
例えば、水漏れしていて住めないとか、電気が通っていない状態はダメということです。
2つ目は、「保存義務」。物件に不具合があったとき、ちゃんと修理してくれる義務のことです。
借主の責任じゃない傷み(例えば、設備の経年劣化など)については、貸主が直す必要があります。
賃借人の義務は何か
一方、借りる側(賃借人)の義務はというと…
・「賃料を払う義務」:これは当然ですね。月末払いが原則です。
・「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」:借りた物件を丁寧に使うこと。普通に掃除したり、壁に穴をあけないように気をつけたり、というのもここに入ります。
・「原状回復義務」も関係してきます(これは次の項目で説明します)。
この「善管注意義務」は、宅建ではよく問われるので要チェックです!
賃借人の原状回復義務
「原状回復義務」は、借りた物件を元の状態に戻して返す、という意味ですが、ここで注意したいのが「自然な劣化」は含まれないということ。
たとえば、家具を置いてできた床のへこみや、日焼けによる壁紙の変色などは、「通常損耗」と呼ばれ、借主が負担する必要はありません。
でも、タバコのヤニで壁紙が変色したとか、ペットが柱をガリガリしたとか、そういうのは原状回復の対象です。
このあたり、実生活でもトラブルになりやすいので、覚えておきたいポイントです。
不動産賃借権の対抗力はどういう場合に認められるか
これ、難しいですが、超重要なので覚えておくと良いです!
不動産の賃借権は、第三者に「ここ、私が借りてます!」と主張(=対抗)できるかどうかが問題になります。
そのためには、「登記」が必要なんです。だけど、実際に賃借人が登記することって少ないですよね。
そこで、民法では「建物の引渡しを受けていれば、対抗力がある」とされています。
つまり、住んでいればOK、ということ!
でも、これは「建物」だけで、土地の賃借権は原則として登記が必要なので注意です。
敷金のポイント
敷金とは、借主が賃貸人に預けるお金のこと。目的は「万が一の損害」への備えです。
たとえば、家賃を滞納したり、部屋をひどく汚してしまった場合に、そこからお金を差し引かれることがあります。
でも、特に問題がなければ、退去時に返還されるのが原則です。
ポイントは
①未払賃料に敷金を充当するかどうか決めるのは賃貸人!
②敷金を返還しなければならないのは明渡完了時!(賃貸借終了時ではない)
あと、原状回復費用との関係も試験に出やすいポイントです!
賃貸者は一体どういう場合に終了するのか
賃貸借契約は、期間満了で終了するのが基本です。
民法上、期間は最長で50年とされています。
期間の定めがない場合、解約申入れ後
①土地→1年
②建物→3カ月
経過すると終了します。
試験ではこの「期間」がよく問われるので要注意です!
損害賠償についての期間の制限
民法上、損害賠償請求には「期間の制限」があります。
例えば、貸主が「部屋をすごく汚された!」と損害賠償を請求する場合、契約が終了してから 1年以内 に請求しなければなりません。
それを過ぎると、基本的には請求できなくなります。
つまり、退去して1年以上経ってから「あの時の壁紙代を払って!」は通用しないということですね。
おわりに
今回の記事では、賃貸借に関する大切な7つのポイントをまとめてみました。
普段何気なく借りているお部屋の契約も、こうして学ぶと見え方が変わりますね。
宅建試験でも出題頻度が高いテーマなので、しっかり押さえておきたいです。
次回は「借地借家法」にも触れていこうと思います!また読みにきてくださいね💪