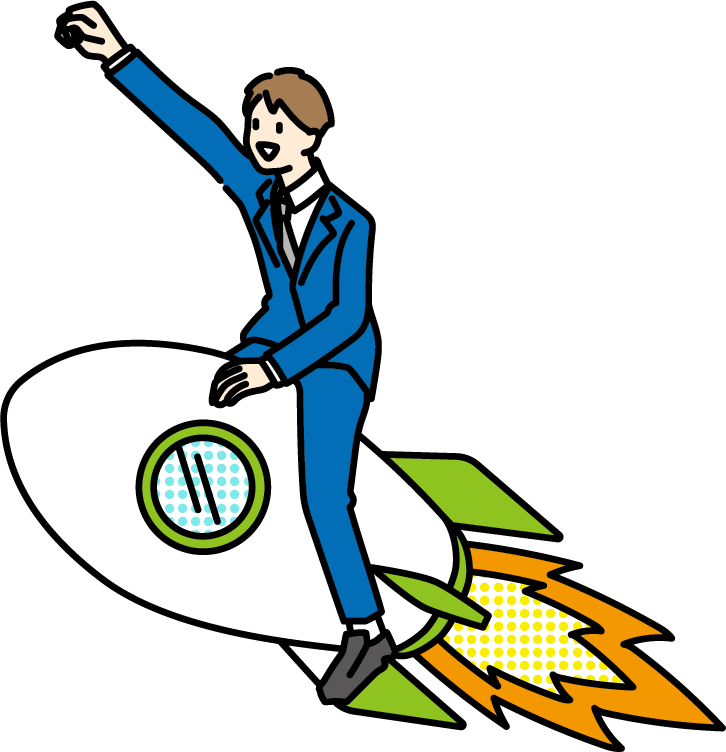今回から宅建業法に入って行きます!
私は権利関係から勉強を始めましたが、宅建業法から入る方も多いかと思います。
宅建業法は不動産の売買や賃貸に関わるルールを決めた法律のことです。
まずは「4つの用語」をしっかり学びたいと思います!
宅建業法で特に重要な「4つの用語」
- 宅地(たくち)とは?
宅地とは「建物を建てるための土地」のことですが、宅建業法では少し広く考えられています。今建物が建っている土地だけでなく、将来建物を建てるために使われる土地も含まれます。たとえば、まだ何も建っていない更地でも、建物の敷地として取引されれば「宅地」です。さらにこれは都市計画法という別の法律で定められた「用途地域」という区域内の土地が対象になります。ただし、道路や公園、河川など公共のために使われる土地は宅地に入りません。 - 建物とは?
建物は家やマンションなどのことです。宅建業法では、「建物の一部分」も建物とみなされます。つまりマンションの部屋1つ1つも対象となります。 - 取引とは?
宅建業法の「取引」には、土地や建物の「売買」「交換」、そして「貸借(賃貸借)」のことを指します。また、これらの「代理」や「媒介」も含まれ、つまり売る側や貸す側の代理人や仲介人として働くことも「取引」に含まれます。 「自ら賃貸」だけは取引に当たりません。免許なしでも、誰でもできます。 - 業(ぎょう)とは?
「業」とは、不特定多数の人に対して反復・継続して宅地建物の取引を行うことです。たとえばお店を構えて不動産の売買や貸借を繰り返し行う場合、これは「業」となります。なお、ここで大事なポイントは、宅建業を営むには国(正確には都道府県知事や国土交通大臣)からの免許が必要ですが、国自体は免許不要で宅地建物取引業はしないということです。 つまり、国が免許を出す側であって営業する側ではない、ということですね。
宅建業を始めるための「免許」と「事務所」について
💫免許は誰が出すのか?
免許は営業をしたい地域によって違います。都道府県ごとに営業する場合は都道府県知事から免許が出ます。複数の都道府県で営業したい場合は国土交通大臣から免許を受けます。営業する場所に変更があれば「免許換え」をしなければなりません。
💫免許の有効期間は?
免許の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続き(更新申請)をしないと免許が切れてしまいます。更新も審査があり、ルールに問題があれば更新できない場合もあります。
更新の手続きは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にやらなければなりません。
💫届出について
免許を受けた後、事務所の新設や移転があった場合は都道府県知事や国土交通大臣に届出が必要です。届出を怠ると罰則があるので注意です。変更が生じたら30日以内に届出なければなりません。
💫欠格事由とは?
免許を受けられない人の条件のことを「欠格事由」と言います。例えば、破産者で復権していない人や、宅建業の免許取消しから一定期間が経っていない人、成年被後見人などが該当します。こうした人は免許が下りません。
💫事務所について
宅建業を営むには「事務所」が必要です。業者は事務所ごとの見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。また、事務所ごとに、従業者の5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
💫案内所について
案内所は「事務所」ではなく、物件の案内や情報提供を行う場所を言います。案内所自体は免許登録の対象ではなく、設置や廃止は届出で済みます。営業の幅を広げるための拠点として利用されますよ。案内所にもいろいろと規制があるので、調べてみてくださいね!
さいごに
宅建業法の入り口である内容については、以上の内容が基本です。
これらを理解することで宅建業法の全体像がつかみやすくなると思います!
細かい点については調べてみてくださいね♪私も復習します〜!